|
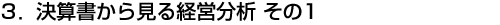
●決算書の仕組みを理解する
貸借対照表(B/S)─
会社の財政状態をつかむ |
|
第○○期貸借対照表(B/S) (画像をクリックすると拡大します)
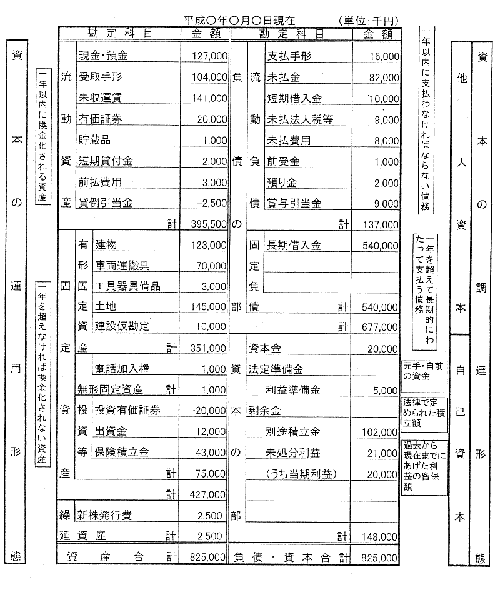
(1)貸借対照表とは(B/S=バランスシート)
一定時点における「資産・負債・資本の状況」を表すもの
B/S
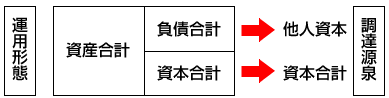
「資産」とは会社の所有する、いわゆる“財産”です。
「負債」とは会社の“借財”です。
資産が会社の所有に属するのに対して、負債は“借財”であるからいずれ返済しなければなりません。
「資産」から「負債」を差し引いた残額が「資本」です。
資本は“正味財産”とも“純財産”とも言われます。すなわち、会社が財産を所有する一方で借財があれば、財産から借財を差し引いたものが正味財産というわけです。
これを計算式で表すと「資産-負債=資本」(一式)となります。
この式はまた「資産=負債+資本」(二式)と表すこともできます。
二式の左側は「資産」で右側は「負債」と「資本」の合計ですが、貸借対照表は、基本的にこの二式で資産・負債・資本の状況を表しています。この表で「資産」合計額と「負債+資本」合計額が同額なことからバランスシート(Balance
Sheet)、略してB/S(ビーエス)と呼ばれます。左右に分けて表す様式を会計では「勘定」といい、この左側を「借方」、右側を「貸方」と呼びます。「借方=左側」「貸方=右側」は貸借対照表だけでなく会計の全てに共通
するルールとなっており、世界共通です。
貸借対照表は見方を変えると、貸方(右側)は資金が“どこから入ってきたか”という「調達源泉」を表しています。借方(左側)は調達された資金が“何に運用されているか”という「運用使途」を示しています。
(2)資産の部の構成
資産の部は大きく3つに分けられます。
1.流動資産
流動資産の内容をみると、「現金」「預金」がありますが、これは手元にある現金と普通
預金、当座預金などです。これらは資金そのものです。これ以外には「受取手形」や、営業収益のうち現金や手形で回収できていない「未収運賃」、燃料、タイヤなどの購入分でまだ使用されていない「貯蔵品」などがあります。
「流動資産」の「流動」は「資金化(現金化)が速い」という意味です。これに対して「固定」は「資金化が遅い」という意味です。言い換えると、流動資産は速く資金化するのに対して固定資産は資金化に時間がかかるということを意味しています。
流動と固定の区分の基準には、次の二つがあります。
(ア)1年基準
・決算期末から1年以内に現金預金になる債権又は費用になるものは、流動資産
(例) 1年もの定期預金 1年以内に返済される貸付金 1年以内に費用化される前払いした賃借料
(イ)営業循環基準
・会社の営業活動により生じた未収運賃、受取手形などの債権
(注)このような資産は、たとえ現金になるのが1年を超えていても、流動資産となります。
2.固定資産
固定資産の部は大きく3つに分けられます。
| (ア)有形固定資産 (イ)無形固定資産 (ウ)投資等 |
|
固定資産には、資産項目のうち、「1年基準」「営業循環基準」から外れたものが表示され、また、基本的に取得価格が10万円以上のものが資産計上(10万円未満のものしか損金計上できない)されます。
(ア)有形固定資産
「有形固定資産」は、文字どおり“形のある”固定資産の意味で、大きく分けると、次の3つに大別
されます。
・減価償却を必要とする有形固定資産
・土地
・建設仮勘定
有形固定資産の内容を見ると、「土地」「建物構築物」「機械設備」「車両運搬具」「工具器具備品」などに分類されます。このうち「土地」だけは減価をしません。すなわち時間の経過に伴う価値の減少は見られないので減価償却をしません。土地以外の固定資産は経年とともに価値が減少するので減価償却をすることとなっており、これら減価償却を要する資産を「償却資産」と呼びます。
(注)建設仮勘定は、建築終了後、耐用年数に応じて償却が行われます。
※「減価償却費」
(イ)無形固定資産
「無形固定資産」は“形のない固定資産”で「電話加入権」などがあります。これは無形の権利で時間の経過とともに減価するものではないので減価償却をしません。これに対して同じ無形固定資産であっても「コンピュータのソフトウエアや営業権」などは、定められた年数にしたがって償却します。
(ウ)投資等
「投資等」は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産のいずれにも該当しないものが表示されます。投資や保証金などが記載されます。
③繰延資産 繰延資産には、創立費、開業費、新株発行費、社債発行費などがあります。これらはすでに費用として支出されたものであるが、その効果
が数期間に及ぶために資産に計上することが特別に商法で認められたものです。
(3)負債の部の構成
負債の部は大きく2つに分けられます。
1.流動負債
「流動負債」には、「支払手形」や、燃料、傭車費の未払額の「未払金」、銀行からの「短期借入金」などがあります。
資産同様、負債も「流動」と「固定」に分けられます。1年基準で区分されるものは、短期借入金、1年以内に返済する長期借入金(1年を超えた返済分は固定負債に区分される)、その他には、未払費用、法人税等引当金など1年以内に支払わねばならないものがあります。また営業循環基準で区分されるものとして支払手形、未払金(買掛金)などがあります。
2.固定負債
「固定負債」の代表的なものは、銀行などからの「長期借入金」があります。これは1年を超えた後に返済期日の到来する借入金のことをいいます。その他には、営業取引以外の支払手形で、決算期後1年を超えた後に満期が到来する「長期支払手形」などがあります。
(4)資本の部の構成
資本の部は3つに分けられます。
これら3つは、返済する義務のない、自前の資金であるという意味から、負債(他人資本)に対して「自己資本」と呼ばれています。
1. 資本金
株主が出資した金額で、経営活動の元手を表しています。個人で事業を起こす場合には、事業主自身が元手をつくらなければなりませんが、会社を設立することによって、外部から新たに出資者を募り、株主として払込をしてもらい、事業に必要な元手を集めることができます。この元手が「資本金」です。
2.法定準備金
「資本準備金」と「利益準備金」から構成されます。「資本準備金」とは株主が出資した金額のうち、資本金に組み入れなかった金額のことで、「利益準備金」とは会社の利益の一部を留保し積み立てた金額です。商法では会社の利益を全額配当せず、その10分の1の額を、資本金の4分の1になるまで積み立てることを義務づけています。
3. 剰余金
「積立金」と「当期未処分利益」とからなり、利益の蓄積額を表しています。積立金には、別
途積立金や任意積立金などとして任意に積み立てられるものの他、役員退職金や配当などの目的(具体的名称)を明確にして積み立てるものがあります。
目次にもどる
|