|
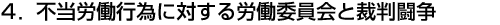
不当労働行為
「不当労働行為」とは、使用者が団結権を侵害する行為であって、労働組合の正当な活動を侵害することをいいます。
労働組合が団体交渉を申し入れたにもかかわらず、使用者側が拒否したり(労組法第7条第2号)組合活動を行ったことを理由に解雇したり、不利益な扱いをすることは出来ません。(同第1号、同第3号)労働組合法では、使用者の反組合的行為を「不当労働行為」として禁止しています。
手続が容易な労働委員会
労働組合法は、不当労働行為を禁止し、これを具体的に救済する為に労働委員会制度を設けています。
具体的手続き
1.労働組合は、救済申立書を作成して組合の資格を証明する書類を一緒に提出
2.労働委員会は、労使双方から事情を聞く「調査」の手続きを行い、争点を明らかにする
3.労働委員会は、証人から事情を聞く「審問」を行う。
4.命令が出る。 |
|
裁判闘争
不当労働行為事件は労働委員会のほか、裁判闘争も考えられます。いずれを利用するかは、弁護士と相談しながら適切に判断する必要があります。
1)裁判手続き
裁判には通常の訴訟手続(本訴)と仮処分があります。後者は本訴を行っていては間に合わない緊急の必要があるとき行う手続です。
2)仮処分
仮処分は例えば組合の委員長が解雇され、本訴の解決を待っていては組合がつぶされてしまうような事態があるとき、「地位
保全の仮処分」を提訴します。 申立人は解雇された本人ですが、組合が全面
的にサポートすることになります。
仮処分は基本的には証人尋問を行わず、当事者の主張や証拠を書面
で提出し、裁判官は書面を見て判断します。労働者の言い分が認められるときは、会社に対して一定期間の賃金の支払いが命ぜられ、これに従わないときは強制執行できます。
3)本訴
(1)本訴というのは、通常の訴訟手続です。仮処分を経ず、はじめから本訴となるときも多く、また仮処分で決着がつかないときも本訴を提起することになります。
裁判の流れは別表「裁判の概要」の通りです。
簡易裁判所は訴額90万円未満の少額の事件を扱うところであり、最近は30万円以下の事件は1回の裁判で終わらせる少額訴訟が話題になっていますが、解雇などを争う労働事件の管轄は地方裁判所です。仮処分も地方裁判所で行われます。
(2)本訴は、申立人(原告)が裁判所に「訴状」を提出することから始まります。本訴では申立人を原告、相手方を被告と言います。
訴状は被告に送達され、第1回目の口頭弁論期日では原告の「訴状」と被告の「答弁書」が正式に裁判の舞台に登場します。このあと裁判は原告と被告の双方が自分たちの法的な言い分を「準備書面
」に書いて主張し、また証拠書類「書証」を提出します。最近の裁判では証人尋問で話す内容も、証人尋問に先立って陳述書という書証として提出することを要求されます。
裁判は初回から3回目位は書面のやりとりと言うべき「口頭弁論」を行うのが原則ですが、最近では単なる書面
の往復ではなく裁判官が主導して双方の言い分を詳しく聞いたり、裁判の争点をはっきりさせる「弁論準備手続」を行うことが多くなってきました。
(3)さて、双方の主張と争点が明確になった段階で「証人尋問」が行われます。裁判のハイライトであり、労働事件では組合の仲間が傍聴に行ったりします。
(4)そして、証人尋問を経て裁判官が「判決」を行います。判決は労働者勝訴の解雇事件であれば以下のような内容になります。
|
判 決
当事者の表示(略)
主文
1.原告が被告の従業員であることを確認する。
2.被告は原告に対し平成15年8月から毎月25日限り金30万円を支払え。
3.被告は原告に対し金150万円およびこれに対する平成15年7月26日以降支払に至るまで年5分の割合による金員を支払え。
4.訴訟費用は被告の負担とする。 5.第2項および第3項は仮に執行することができる。
理由(略)
|
|
(注1)第1項で従業員の地位確認=解雇無効であることが明らかにされます。
(注2)第2項は提訴以降の毎月の賃金の支払いを命じたものです。
(注3)第3項は提訴以前の未払賃金(本訴では1ヶ月30万円で5ヶ月分)の支払を命じたもので第2項と合わせて賃金の支払いを命ずる内容です。
(注4)第4項の訴訟費用の中に弁護士費用は入らないのが原則です。従って労働者が勝っても弁護士費用は自分持ちで、また負けても会社側弁護士の費用は負担しません。
実は現在民事訴訟法改正論議の中で弁護士費用も敗訴者に負担させようとする提案が政府からなされていますが、弁護士会や労働組合は反対しています。力の弱い消費者や労働者が敗訴者負担をおそれて訴訟を起こすことをためらう可能性があるからです。
(注5)判決は原則として確定したときに効力が発生します。従って被告が控訴(高等裁判所)、上告(最高裁判所)と引き延ばしをはかれば延々と引き延ばすことが可能となります。そこで金銭の支払等に「仮執行宣言」がつき、確定しなくても一審判決を実行できることになっています。
4)控訴
一審判決に不服があるときは高等裁判所に「控訴」できます。但し控訴審は一審判決のチェック役ですから、一審判決が相当程度不当なものでなければ一審と同じ結論になります。
5)上告
控訴審判決に不服なときは最高裁判所に「上告」できます。しかし上告理由は憲法違反や判例違反等に限られていますから、余程のことが無ければ控訴審と同じ結論になります。
目次にもどる
|