|
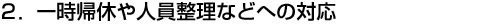
(1)休業・一時帰休
休業や一時帰休は、主に在庫調整を目的としていて、雇用調整に直接結びつくものではありませんが、問題は休業期間中の賃金保障です。労基法(第26条)では、平均賃金の60%以上と定められていますが、これを最低として、できる限り高くすることが必要です。

(1)事前協議のなかで、実施期間・対象人員・解消計画を明示させる
(2)できる限り全体で公平に実施させるように配慮させる
(3)賃金保障は、所定内賃金の100%を原則に、最低でも90%を確保する。また、雇用調整助成金の適用を受ける場合は100%保障とさせる
|
|
(2)配転・出向
組合と経営者が集団的に労働契約を結んでいる以上、人事権があるからといって、勤務態様(労働の場所・種類・時間)の変更について、場合によって組合および組合員の同意なしに命令することはできません。
出向には在籍出向と移籍出向があります。移籍出向というのは、別
会社が雇用者となるわけですから、労働者の同意が必要になります。(民法第625条)

(1)事前協議のなかで、業務上これを必要とする理由、要員計画、期間などを明らかにさせ、とくに、期間についてはできる限り短期間とさせる。
(2)配転・出向者の選定・取扱いについては、公平・平等を原則に、本人の事情を十分に考慮し、必ず本人の同意を得て決定する。
(3)新たに技術を習得する必要がある場合には、必要期間、十分な教育・訓練を実施させる。
(4) 本人に対する提示は、少なくとも1ヶ月前とし、諸手当の整備、帰省のための旅費など、細部にわたって条件を確立する。
(5) 他府県にまたがる配転・出向の場合は、住宅の確保・保障・子弟の転校などについても必要な措置を講じさせる。
(6)出向先の労働条件と現行の条件の間に不利な差がある場合は、現行の労働条件を保障させるとともに、将来の昇進・昇給など不利益が生じないようにさせる。
(7) 組合員の資格は保証し、必ず苦情処理委員会を設置する。
|
|
Q&A「事業所の統廃合と一部廃止」
(3)希望退職
希望退職というのは、「希望」という名をかりた人員整理です。希望退職を募ること、それ自体が会社の体質や、労働者の労働意欲、相互の関係などに大きな影響を与えます。したがって、組合としては、よほどの事情がない限り認められるものではなく、安易な実施や見切り発車などの事態は、絶対に容認してはなりません。

(1)会社より諸資料の提出を求め、その原因を客観的に明らかにさせ、希望退職以外の解決策はないのかを検討し、交渉する。
(2) 原因と先行き見通し、希望退職以外の解決策がないことが明らかになるまでは、退職条件について交渉しない。
(3) 「組合との協議・合意」協定を会社と締結する。
|
|
希望退職以外に方法がない場合のポイント
(1)対象人員を最小限とし、公平・平等・自由の立場から退職者を募る
(2)退職条件として、特別退職金の引き上げ、解雇予告手当、有給休暇の保障など、できる限り有利な条件を保障させる。
(3)希望者が予定人員に達しなかった場合は原則として打切りとさせ、それ以降の対策については、組合と協議することを明確にさせる
(4)退職者に対する社宅の取扱い、帰郷者に対する旅費保障など、細かい点にも配慮させる
(5) 再就職のあっ旋は会社の責任とし、経営者が努力して行う。組合としても、地域の仲間を通
じて協力要請するなど、側面から協力する
(6) 組合は、退職後の追跡調査を行い、将来とも組織の問題として対処する
(4)人員整理
労働者を解雇するには、労基法・労組法などの法的な制限があることはいうまでもありませんが、経営上の理由がある場合でも、一定の条件が必要になります。
裁判所の主な判例では、次の4つの要件を要求しています。
なお、労働協約や就業規則などで、解雇事由や手続きについて使用者に制限が課せられている場合は、もちろん、それに制約されます。
Q&A「会社分割」
整理解雇の4要件
| 1.整理解雇の必要性 |
会社の維持・存続をはかるために人員整理が必要で、かつ、最も有効な方法であること
|
| 2.解雇回避の努力 |
新規採用の中止、希望退職の募集、一時帰休の実施など、会社が解雇回避のための努力をしたこと |
| 3.整理基準と人選の合理性 |
どんな人を解雇するかの基準が合理的、かつ公平でその運用も合理的であること |
| 4.組合や労働者との協議 |
解雇の必要性や規模・方法・整理基準などについて十分説明して、組合や労働者の納得を得る努力をしたこと |
|
目次にもどる
|