|
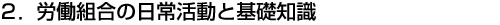
労使関係の安定と事業主の姿勢
労働者を雇用している場合、事業主としては、労働者の種々の要求に配慮しながら、企業の実状に沿った事業運営を行う必要があることはいうまでもありません。労使関係が安定してこそ、事業の発展が期待できるといえます。この労使関係の安定にはいろいろな方法が考えられますが、やはり個々の労働者の要望を把握し、それに適切に対処していくことが重要です。そしてその場合、労働組合との交渉などを通じて労働者の意見・要望をつかみ、対応をはかっていくことが効果的です。
労働組合とは
憲法では勤労者の「団結権」「団体交渉権」「争議権」―いわゆる労働三権―を保障しています。
労働者と事業主(使用者)は、対等の立場で労働条件などを決めるのが原則ですが、実際には労働者個人は使用者より弱い立場に立つことが多く、労働者が個々に使用者と交渉しても、労働者に不利な条件となりがちです。このような労働者の弱い立場を考慮して、憲法ではこれらの労働者の権利を保障しているわけです。
労働組合をつくる場合、特別の手続きや届出は必要ありませんが、労働組合法上の労働組合と認められるためには、次のような要件を満たしていることが必要で、それを満たす場合には、労働組合法による種々の保護が与えられます。
(1)労働者が主体となって自主的に組織する団体であること
(2)労働者の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上をはかることを主たる目的とする団体であること
(3)労働組合法第5条に規定されているような民主的な規約を備えていること
団体交渉
団体交渉は、労使の賃金や労働時間などの意見対立を調整し、それを通じて労使間の紛争を未然に防ぐ役割をもっており、その対象となるのは労働条件その他労使関係に関する事項です。使用者が団体交渉を正当な理由なく拒むと、不当労働行為となります。また、組合側は、上部団体の役員などに団体交渉を頼むこともできます。
労働協約
労働協約とは、団体交渉の結果到達した労働条件その他労使関係に関する事項についての合意を文書に作成し、労使が署名または記名押印したものをいいます。その有効期限は3年以内です。
労働協約で決められた労働条件と、就業規則や労働契約で定められた内容が違っている場合は、労働協約が優先します。また、労働協約で決めた事項は、協約当事者に適用されるのが原則ですが、特例として、他の労働者に拡張して適用される場合もあります。
争議行為
争議行為とは、労使が団体交渉を行い、双方の主張にくい違いがあるとき、その主張の実現のために行う行為で、業務の正常な運営を阻害するものをいいます。
形態としては、ストライキ(同業罷業=集団で労働力の提供力を拒否)、スローダウン(怠業=仕事の能率を低下させる行為)、ロックアウト(事業所閉鎖=争議行為に対抗して行う使用者の行為)などがあります。
不当労働行為
労働組合法は、労働者の団結権、団体交渉権や争議権を守るため、次のような使用者の行為を不当労働行為として禁じており、被害をうけた労働組合や労働者は、労働委員会に対して救済の申し立てをすることができます。
| 不利益取扱い |
労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入したり、労働組合を結成しようとしたこと、その他労働組合の正当な行為をしたことを理由に、解雇・その他の不利益な取扱いをすること |
| 黄犬契約 |
労働者が労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退することを雇用条件とすること |
| 団体交渉の拒否 |
使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否すこと |
| 支配介入 |
使用者が労働組合の結成・運営を支配したり、これに介入することや、労働組合運営経費を援助すること
|
| 労働委員会の手続き関与を理由とする不利益取扱い |
労働者が労働委員会に不当労働行為の申し立てをしたこと、不当労働行為事件に関する労働委員会の調査や審問・争議調整に際して、労働者が証拠を提出したり発言したことを理由に不利益取扱いをすること |
|
※労働委員会とは
※労政事務所とは
目次にもどる
|