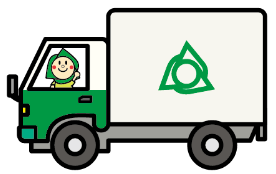活動報告
第55回運輸問題研究集会(10月15日~16日)

現状を的確に捉え、変革に挑戦していこう!
運輸労連は10月15日(水)~16日(木)の2日間、新潟県湯沢町「NASPAニューオータニ」にて第55回運輸問題研究集会を開催。全国から282名(うち女性15名、女性参画率5.3%)の仲間たちが参集しました。
主催者あいさつに登壇した成田中央執行委員長は、政治の状況について、7月の第27回参議院議員通常選挙では与党が過半数を割る結果となり「国民が与党に『NO』を突き付けた」と分析しつつも、私たちが支持する立憲民主党が「与党に対峙するもう一つの選択肢になり得なかった」と総括。ただ、大きな岐路に立つ日本の政治は「チャンスからチェンジを成し遂げていく千載一遇の機会」として、「大きな変化」が生まれることへ期待を示しました。
物流を取り巻く環境については、トラックドライバーの働き方改革を目的とした「物流2024年問題」が社会的に取り沙汰されたことにより、「新物流2法」の成立など、私たちを取り巻く環境も大きく変化しています。さらに2025年6月に成立した「トラック適正化二法」の4つの重要なポイント(「事業許可の更新制」「適正原価の導入」「再委託の制限」「白トラ対策の強化」)が、運輸産業を維持していくため、また私たちの賃金や労働環境を改善するために必要不可欠な制度であると述べました。「物流の2030年問題」も見据え「魅力ある産業・笑顔あふれる産業の実現に向け、運輸労連一丸となって、一層の取り組みを図っていきます」と決意を述べました。
春季生活闘争については、「過去30年で最高の解決額」と評価しつつも、他産業との格差拡大や物価高騰の長期化懸念から「運輸労連として、来年、再来年、さらにその先も継続したしっかりとした賃上げが必要」との考えを表明。2026春闘の構想に向けた「運研集の中での十分な論議」を求めました。
最後に組織拡大については、労働組合の推定組織率が調査開始(1947年)以降で最低となる中でも「労働組合は『必ずそばにいる存在』であり続けていたい」と中央・地方一体となって組織拡大の取り組みを強化するよう連帯を呼びかけました。
講演では、流通経済大学 流通情報学部教授・矢野裕児氏による第1講演「日本の物流の未来〜持続可能な形に変革できるか〜」、連合 総合組織局 組織拡大局 中央オルガナイザー・大磯扶三彦氏による第2講演「組織の強化と拡大に向けて~組合役員として今何ができるか~」を受講。その後、翌日の各分科会に関する問題提起を杉山中央書記長が行い、1日目が終了しました。
2日目は、3つの分科会に分かれての討論。第1分科会(労働政策)は「賃金・労働条件の改善に向けて」をテーマに、2026春季生活闘争や総労働時間の短縮に向けた取り組みなどについて。第2分科会(産業政策)は「当面する政策課題への対応」をテーマに、「貨物自動車運送事業法の一部改正」への対応などについて。第3分科会(組織)は「組織強化と拡大に向けて」をテーマに、組織拡大や強化に向けた取り組みについて。各分科会で現場報告や今後の展望など、活発な討議が行われました。
写真一覧